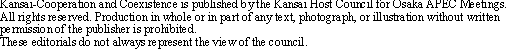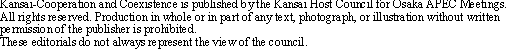

日本固有の宗教である神道では、その宗教的行事が祭りだった。地域共同体に
とって連帯の絆の確認ともなり、人々もさまざまな催しにつかの間の解放を感
じ、それを心待ちにしたため、しだいに盛大なものになっていった。
中でも、日本を代表する三大祭りが、東京の神田祭、大阪の天神祭、京都の祇
園祭である。
天満宮の祭りである天神祭は毎年、7月25日を中心に行われる。クライマック
スは、神輿を船に乗せて川を渡る「船渡御」で、船上では神楽や舞楽などが奉
納され、100隻以上の船が次々と堂島川から大川を遡っていく。
天神祭が水の都と呼ばれる大阪の特徴を生かした「動く劇場」ともいえる祭り
なのに対し、祇園祭は京都の中心部を鉾山が巡行するいわば「動く美術館」と
もいえる祭りである。八坂神社の祭礼で、7月17日に行われる。
9世紀に都に疫病が流行った際、鉾をたてて疫病退散を祈ったのが始まりとさ
れ、その後、町衆がそれぞれの町内から山車の豪華さや奇抜さを競うようにな
り、ほぼ現在の姿になった。
この祇園祭を含めて京都の三大祭りと呼ばれているのが、葵祭と時代祭である。
歴史を伝える祭としてユニークなのは、毎年秋に大阪の四天王寺を舞台に繰り
広げられる古代史祭り「四天王寺ワッソ」である。「ワッソ」は「ワッショイ」
の語源ともいわれる韓国語で「来た、来られた」という意味とされている。
四天王寺は飛鳥時代に聖徳太子によって建てられ、当時の国際外交の桧舞台と
して、文化交流の窓口になっていた。百済や高句麗の僧や技術者が次々に訪れ
て日本の国づくりに貢献した。聖徳太子は使節団を手厚くもてなし、日韓友好
の懸け橋となった。
このような歴史を若い在日韓国人や日本人に知ってもらおうと、在日韓国人を
はじめ、関西経済界も積極的に協力、1990年に祭りが始まった。いまでは、日
本とアジアの共生を目指す時代絵巻として定着、浪速の秋を彩る名物行事にな
っている。
大阪、京都だけでなく、それぞれの地域にも歴史の中で生まれ、今日まで守り
継がれてきた祭りがある。そこに、人々は五穀豊穣、商売繁盛、家内安全を託
している。1月10日に西宮神社(兵庫県西宮市)や今宮神社(大阪市)など各
地で行われている「えべっさん」と、秋に各地で行われるだんじり祭などはと
りわけ有名である。だんじり祭は、ほぼ300年の歴史があり、町中で参加する
庶民のイベントである。中でも、9月14、15日の大阪府岸和田市のだんじりは
スピード感にあふれ、日本国内だけでなく、外国からの見物客が増えている。
そのほか、400年の歴史を持ち、毎年130万人を超える内外からの観光客が訪れ
る徳島の阿波踊りは、和楽器が奏でる軽やかなリズムにのって、怒涛のおどり
絵巻が繰り広げられる。熊野那智大社(和歌山)の火祭りは、境内の石段上で
高さ10mの扇神輿が大松明で清められる様子は圧巻である。また、女装した町
内の若者が山車をかついで町内をねり歩く近江八幡の左義長祭は全国的によく
知られている。
このほか、3月13日の奈良二月堂のお水取のように関西に春の訪れを感じさせ
る行事もあり、人々はこうした祭りや行事を通し、季節感をも実感している。