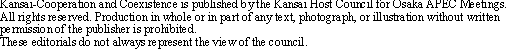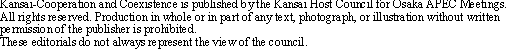

大阪が、日本の金融拠点として機能し始めたのは江戸時代からである。当時
の大坂は、米をはじめとする全国の物資の集散地であるとともに、江戸への物
資供給地であった。商品生産の盛んな関西の諸都市や富裕な農村を後背地に持
っていたことと、大消費都市、江戸との定期航路が開かれたことが有利に働い
た。大坂は、まさに全国経済の中心「天下の台所」であり、「諸色値段相場
の元方」であった。全国規模の商品の流通にともない、取引決済、為替、手
形の発行といった業務が増加した。それを専門にする両替商が台頭してきた。
彼らは、江戸幕府を倒した西南雄藩に対しても貸付を行っており、明治維新を
乗り切って、近代的な銀行に姿を変えた。大阪には、全国で初めて手形交換所
が開かれるなど、活発な金融機能が維持され、大阪の主要産業は、以後こうし
た銀行の支援を受けながら成長してきた。
20世紀はじめ、数度の金融恐慌を経て銀行は淘汰され、財閥系を頂点とする今
日の姿がほぼ出来上がった。
住友銀行は住友グループの中核で、収益力では都市銀行トップクラスに位置す
る。
非財閥系で、上位都市銀行の地位を保っている三和銀行は、戦後、中位の銀行
3行が合併したものだが、そのうち1行の鴻池は、江戸時代の有力な両替商か
ら発展してきた。また大和銀行は、都市銀行では、唯一信託を併営している。
その他、世界有数の銀行となった、さくら銀行の前身の一つである神戸銀行
は、1936年の発足以来、神戸に本店を置き地元の発展に貢献してきた。
一方、関西では、中小企業の比重が大きいことから、中小企業金融を主な業務
としている第二地方銀行、信用金庫、信用組合が発達した。大手の第二地方銀
行は、中堅の地方銀行と変わらない資金量を持っている。
近年は、関西の持つ経済力に着目した外国銀行の進出も盛んで、1980年の14行
が、91年には31行に、店舗のみならず事務所を設置する銀行も4行から9行に急
増した。関西国際空港の開港を機に、国際金融都市機能のさらなる充実を目指
している。
各家庭へのパソコンの普及にともない、個人顧客を対象とした新しいサービス
として導入されたのが、ホーム・バンキングである。銀行のコンピュータと家
庭の端末を電話回線で結び、家庭にいながら預金の残高照会や振込を行うこと
ができる。
一方、企業と銀行のコンピュータを通信回線で結んでデータのやりとりを行う
ファーム・バンキングも行われている。銀行のコンピュータとデパートなど
小売店のレジスターを通信回線で結び、買物客が銀行のキャッシュカードをレ
ジスターに付いているカードリーダーに読み取らせると、買物代金が即座に客
の預金口座から、デパートなどの口座に振り替えられるという銀行POSも導
入されている。